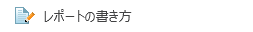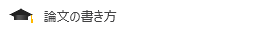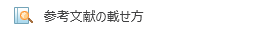資料紹介
【東洋大学】
課題:日本の戦前戦後の道徳教育の歴史的変遷について説明せよ
3000字以内で説明する課題
合格認定された論文です。使うべきキーワードについても説明しており、テキストを熟語くしていることがわかるとの評価をいただきました。
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
日本の道徳教育の戦前戦後の歴史的変遷について説明せよ。
はじめに
本レポートでは、戦前と戦後の二期に分け、日本の道徳教育の歴史的変遷について述べる。
①戦前における道徳教育の歴史的変遷
(1)修身科が成立する以前の道徳教育
明治時代の幕開けとともに五箇条のご誓文が出され、王政復古と神道・国学の復活がなされた。1872年、日本で最初の学校制度を定めた教育法令である学制の制定により、全国に設置された学校における教育内容が提示された。小学校における修身口授という科目は、近代教育における道徳教育の原点となった。その教授法は、欧米の倫理書等の翻訳書を資料としてその文意を教師が説明する口授形式がとられ、江戸時代からの儒教的徳目を掲げる内容が教授された。儒教の基本理念である義は、武家社会での主人に対する絶対的服従および庶民の武士階級への服従として非常に有効であった。このような欧米の教育制度を参考にした教育制度は、当時の日本の社会生活が考慮されたものではなく、焼き打ち事件の発生や自由民権運動の急速な進展等をもたらした。新たな教育制度の確立が課題とされ、伝統的な儒教に基づく道徳教育の確立が図られ...
tsu_shin_kyo_ikuの資料(110)
販売者情報
上記の情報や掲載内容の真実性についてはハッピーキャンパスでは保証しておらず、
該当する情報及び掲載内容の著作権、また、その他の法的責任は販売者にあります。
上記の情報や掲載内容の違法利用、無断転載・配布は禁止されています。
著作権の侵害、名誉毀損などを発見された場合はヘルプ宛にご連絡ください。