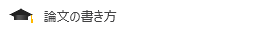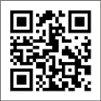資料紹介
留岡幸助(以下、留岡)は、幕末の1864年の岡山県高梁市に生まれた。吉田万吉、トメの子として生まれ、生後まもなく、留岡家の養子となる。留岡家は米屋を営んでいた。
当時、留岡は子供同士の喧嘩で武家の子どもを怪我させ、商いに支障が出て、養父から厳しい折檻を受け、家出する。高梁のキリスト教会に逃げ込み、やがて18歳で洗礼を受けた。
留岡がキリスト教に出会い、のめりこんでいったきっかけは、「面白そうだから聴きに行こうよ」という友達の誘いで喜んでついて行ったことから始まる。外国人一人、日本人二人が代わる代わる講釈をしている。
周囲の静かに講釈を聴いている大人に圧倒され留岡もしっかりと耳を傾けた。〈西洋の軍談講釈というのは、日本のやり方とは随分違うんだ〉と不思議に思いつつも、4、5日通い続け、ある日の講釈が留岡の心をがっちりととらえたのである。
-士族の魂も、商人の魂も、神様の前ではみな同じ価値がある。値打ちは同じである。-
留岡にとっては決定的な言葉であった。そのとき、またしても幼い時の屈辱的な体験が思い起こされた。このとき初めて、これまで抱いてきたわだかまりが、解けたように思ったと留岡は感じている。そして、もっとこのキリスト教の教えを知りたいと深く思い、学びへの情熱をなおいっそう燃えたぎらせた。
1885年同志社英学校別科神学科邦語神学過程に入学した。新島襄の教えを受けた。卒業後、丹波協会の牧師となった。
そこに、北海道空知集知監から教誨師の依頼が舞い込んだ。教誨師とは、刑務所の中で受刑者に対して、徳性の育成を目指した教育活動を行う者。教会員・親族はこぞって反対したが、1891年留岡は北海道に渡った。
そこで留岡は、監獄の惨状を目の当たりにすることになる。全身真っ赤な囚人服をまとい、鎖につながれて鎖の先に重い鉄玉をひきずり作業する姿は、人を猛獣とみなした非人間的な取り扱いに見えたという。また、監内では、陰惨な事故も絶え間なく続いた。最も悲惨なのは、採炭現場である。落盤や 爆発が頻発していた。そのために外傷性の怪我人のみならず、死者がおびただしく発生していた。当時、逃亡防止のため、あらゆる杭口に金網や柵が張られていたので、いったん大事故が発生すると囚徒はまったく逃げ場がなく、その場で死を待つしかなかったのである。
留岡はこの惨状を見、〈彼らは、何を思いつつ死んでいったのだろう。絶望の思いのままにか、それとも遣り場のない怒りを抱いたままか…。親も妻子も兄弟も、恐らくはいただろうに〉
同時に留岡は、囚人達の個別的な教誨を行う中で、囚人の70%から80%が、12、3歳の頃にはすでに不良少年であり、その背景には重大な家庭問題、劣悪な生育環境が存在するということを見出した。
彼は後年になって、このとき「天啓の如き閃き」を感じたと述べている。当時の非行少年に対する処遇は成人と同様の厳罰主義・応報主義だったが、彼は非行の原因は家庭および社会にあるのであり、非行の対策は純粋に教育の課題ととらえるべきだと考えるにいたった。
留岡は、現場の実態のみならず、数々の事故の記録を克明に手帳に書きとめた。医務所や病監での病因の実態を調査した。調べてみると、事故による死傷者がとても多かった。
留岡は、この現状を見て自らの無力さにいらだちながら何ができるか、また彼らを人間扱いしてほしい、望みを持てるように監内を整備して欲しいと思い、申し入れをしたが、まったく取り合ってもらえなかった。
日本では、「日清戦争以前に在りては斯業尚ほ頗る幼稚にして」(布川孫市)と言われていた慈善事業が、19
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
留岡幸助(以下、留岡)は、幕末の1864年の岡山県高梁市に生まれた。吉田万吉、トメの子として生まれ、生後まもなく、留岡家の養子となる。留岡家は米屋を営んでいた。
当時、留岡は子供同士の喧嘩で武家の子どもを怪我させ、商いに支障が出て、養父から厳しい折檻を受け、家出する。高梁のキリスト教会に逃げ込み、やがて18歳で洗礼を受けた。
留岡がキリスト教に出会い、のめりこんでいったきっかけは、「面白そうだから聴きに行こうよ」という友達の誘いで喜んでついて行ったことから始まる。外国人一人、日本人二人が代わる代わる講釈をしている。
周囲の静かに講釈を聴いている大人に圧倒され留岡もしっかりと耳を傾けた。〈西洋の軍談講釈というのは、日本のやり方とは随分違うんだ〉と不思議に思いつつも、4、5日通い続け、ある日の講釈が留岡の心をがっちりととらえたのである。
-士族の魂も、商人の魂も、神様の前ではみな同じ価値がある。値打ちは同じである。-
留岡にとっては決定的な言葉であった。そのとき、またしても幼い時の屈辱的な体験が思い起こされた。このとき初めて、これまで抱いてきたわだかまりが、解けたように思ったと留岡は感じて...