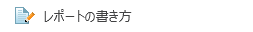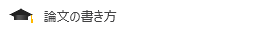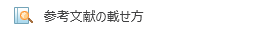資料紹介
【佛教大学:日本文学史】リポート:第1・第2設題
●第1設題
「上代、中古、中世、近世の文学の特質を、それぞれの時代の特性をふまえつつ、下記の諸作品を例にして具体的に説明せよ。」
〈古事記・万葉集・古今和歌集・女流日記・源氏物語・平家物語・徒然草・近世小説〉
●第2設題
「明治、大正、昭和の文学の特質を、それぞれの時代の特性をふまえつつ、下記の各文学思潮を例にして具体的に説明せよ。」
〈写実主義・擬古典主義・浪漫主義・自然主義・余裕派(高踏派)・耽美派・白樺派・新思潮派・プロレタリア文学・新感覚派〉
フィードバック内容:
「テキストのポイントをよく押さえており、リポートにもその点がきちんと反映され、読みやすくまとめられたリポートになっている。」
との評価でした。
リポート作成の際の参考にお使いください。
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
第1設題
「上代、中古、中世、近世の文学の特質を、それぞれの時代の特性をふまえつつ、下記の諸作品を例にして具体的に説明せよ。」
〈古事記・万葉集・古今和歌集・女流日記・源氏物語・平家物語・徒然草・近世小説〉
古典とは主に上代、中古、中世、近世までの文学を指す。本リポートは、それぞれの時代の特性を踏まえつつ、各時代の作品を例に挙げて説明し、文学の歴史を指定テキストの内容に沿ってまとめるものである。ここでは作品例として、『古事記』、『万葉集』、『古今和歌集』、女流日記の実態、『源氏物語』、『平家物語』、『徒然草』、近世小説の全体像を解説していく。
一、上代
口承文学の誕生から平安遷都までを上代と呼び、文学は口頭による伝承の中から誕生した。言霊信仰により、祭りの場で使われる言葉は格調高く整えられ、表現にも工夫が凝らされた。この祭りの場では身近に起こった出来事が神に関連付けて語られ、それが「神話」となった。
漢字の伝来により万葉仮名が考え出され、神話や歌謡は文字となって書き留められていくようになり、八世紀初頭には現存する最古の書物『古事記』が編纂される。神話的側面の強い上巻...