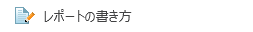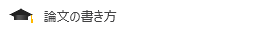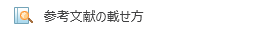資料紹介
こちらは、2019年度~2022年度(過年度)のリポート課題です。
現在の課題、あるいは科目修得試験に向けて利用できる可能性がありますので、参考にしていただければ幸いです。
なお、丸写しはお控えください。
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
美術史(科目コード:B11400)課題2
鎌倉時代の彫刻について、運慶、快慶など慶派の仏師の作例をあげて述べなさい。
〈ポイント〉
鎌倉時代になると、平安時代後期の仏像とは全く異なる新しい様式の仏像が慶派の仏師によって制作された。慶派の中でも、運慶と快慶ではそれぞれに違いがあるので、作例をあげ特徴を捉えながら述べること。
〈キーワード〉
慶派、運慶、快慶
〈参考文献〉
『カラー版 日本仏像史』水野敬三郎(美術出版社)
鎌倉時代は、武士が台頭する一方で、旧来の貴族勢力が、彼らと争いながら自らも変質を遂げていった時代である。
美術の世界では、平安末期の観念的かつ耽美的な傾向が深まる中で、現実感や実在感を求めた表現が胎動し始める。それは早く彫刻において現れ、二十五歳の若き運慶が天賦の才を表し、以後仏師界を牽引する。彼ら慶派仏師がその活動を飛躍させたのは、一一八〇年の平重衡による南都焼討の後の、東大寺・興福寺の復興作業であった。中でも一二〇三年の東大寺南大門金剛力士像は、その雄々しい巨大さにおいて、代表的な作品となっている。運慶らの量感豊かで力強い作風は、武士の好みに合致し、彼らの活...