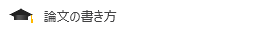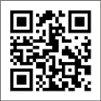資料紹介
トーマス・マンに見るドイツの「内面性」と第二次世界大戦
「ドイツ」と聞いて私たちが思い浮かべるのはどんなイメージだろうか。そこから生み出された音楽や文学、そして絵画などの、他の国には例を見ないほどの優れた芸術性か。あるいは二度の世界大戦において世界の厄介者となり、第二次世界大戦では口にするのも憚られるほどの残虐性を見せたことであろうか。その二つは、一見すると相容れない、矛盾するドイツの姿のようである。しかし、トーマス・マンが「悪しきドイツと良きドイツと二つのドイツがあるのではない」と述べているように、それら二つはいずれも、共通の「ドイツ性」によってはぐくまれた結果であるとも見ることができる。マンは、『ドイツとドイツ人』の中で次のように述べている。
ドイツ人は西欧に――その最も美しく、人間同士を最もよく結びつける音楽とは申しませんが――その最も深遠でもっとも意味深い音楽を贈りました。そして西欧はドイツ人に、そのことに対する感謝と賞賛を惜しみませんでした。しかし、西欧はまた同時に、このような魂の音楽性が他の領域において――政治の領域、人間の共同生活の領域において――高価な代償を支払って得たものであることも感じておりましたし、今日、これまでにもまして強く感じています。
ドイツの持つ比類なき独特の音楽性―最も深遠で最も意味深さを含むもの―は、同時に芸術以外の政治や人間的なかかわりの場面においては必ずしも良いものばかりを生んできたわけではない。むしろ、憎むべき結果までをももたらしたのである。いったいその音楽性とは、内面性とはどういったものなのであろうか。
そうしたドイツの内面性を内包した人物、「ドイツ的本質の巨大な化身」として、マンは宗教改革者ルターを挙げた。ルターはその極めて反ローマ的、反ヨーロッパ的活動によってプロテスタント的自由や宗教的解放を呼び起こした。しかし、これらの活動は決して非キリスト的、異教的な気質からきたのではないとマンは述べている。
ドイツは、キリスト教をこの上なく真剣に受け取ったのです。キリスト教は、他の国ではもはや真剣に受け取られなくなっていた時代に、ドイツ人ルターにおいて小児のごとく農民のごとく至極真剣に受け取られました。ルターの革命がキリスト教の命脈を保たせたのです。
このことはドイツ人の理想主義的、真理を極端に厳格に受け取るという性格をよく示している。しかしながら、ルターは確かに自由の英雄、キリスト教者の自由を復活させた者であったけれども、政治的自由や市民の自由については極めて無知かつ鈍感であり、むしろそういったものを求める要求や運動を激しく憎んだ。マンはこのことに対して、ルターは農民一揆を、宗教的解放を危険にさらすものとしかみなかったからであると述べている。それは真実かもしれない。付け加えて言うならば、ルターは革新者であったと同時に「すべての人は、上に立つ権威に従え!」というパウロの言葉に代表されるような保守的信念の持ち主であったがゆえにそういった運動に対して本能的な嫌悪感を覚えたのではないかという推測もできるだろう。さもなければ「農民を狂犬のように打ち殺せと命じ、諸侯たちに対して、今こそ土百姓どもを虐殺し、絞殺することによって天国を手に入れることができるのだと呼びかけ」たりなどといった、理性的とは言いがたいまでの激しさはもたなかったのではないだろうか。ルターに見られるこのような矛盾、内部葛藤はそれ自体ドイツ的で、ドイツの根底に流れる「 」な音楽性を示しているように思われる。小児のような純粋さで真理を厳しく追及していく姿勢を
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
トーマス・マンに見るドイツの「内面性」と第二次世界大戦
「ドイツ」と聞いて私たちが思い浮かべるのはどんなイメージだろうか。そこから生み出された音楽や文学、そして絵画などの、他の国には例を見ないほどの優れた芸術性か。あるいは二度の世界大戦において世界の厄介者となり、第二次世界大戦では口にするのも憚られるほどの残虐性を見せたことであろうか。その二つは、一見すると相容れない、矛盾するドイツの姿のようである。しかし、トーマス・マンが「悪しきドイツと良きドイツと二つのドイツがあるのではない」と述べているように、それら二つはいずれも、共通の「ドイツ性」によってはぐくまれた結果であるとも見ることができる。マンは、『ドイツとドイツ人』の中で次のように述べている。
ドイツ人は西欧に――その最も美しく、人間同士を最もよく結びつける音楽とは申しませんが――その最も深遠でもっとも意味深い音楽を贈りました。そして西欧はドイツ人に、そのことに対する感謝と賞賛を惜しみませんでした。しかし、西欧はまた同時に、このような魂の音楽性が他の領域において――政治の領域、人間の共同生活の領域において――高価な代償を支払って得た...