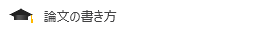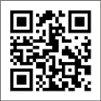All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
『<民主>と<愛国>』 第14章
「公」の解体
この第14章、「公」の解体では吉本隆明を中心として取り上げ、戦後知識人の革新ナショナリズムと、彼の個人的戦争経験がもたらした思想の二点について検証されている。
吉本は「戦中派」の知識人であり、敗戦時に10台後半から20代前半の思春期を過ごした世代である。彼らは丸山ら「戦前派」とは異なり、戦争状態や皇国という概念自体を当たり前のものとして成長しており、思想や経験に偏りがある。「戦中派」は戦争こそが正常であり、平和の方が異常だという考えをしばしば述べた。彼らは「戦死」に憧憬を抱き、降伏を決定した為政者への憎悪を有して権威や国家への反感、懐疑、反発が根底に存在している。またそういった権威的な象徴とみなされた進歩的知識人への反発もあった。だが、「戦前派」からすると、「戦中派」は極めて無教養に映り、敗戦直後には「空白の時代」とも揶揄していたほどであった。「戦中派」の最大のよりどころは、戦争にネガティブであったにもかかわらず声を上げてこなかった年長者らの責任追及し、彼らを「卑怯」であると攻撃をすることであった。...