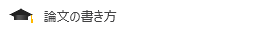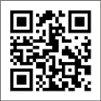資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
written by Hiroko OZAKI 評論・尾崎弘子 The deer who has a small corner -A short essey about AIZU YAICHI 小さな角(つの)を持った鹿
― 會津八一試論
一 ホトトギス
會津八一の文学者としての出発は、「ホトトギス」であり子規の写実であると言ってよいだろう。明治一四年、新潟の大きな家に生まれ育った八一の文学への関心は、市の助役を務めていた学問好きの叔父友次郎からの影響によるところが大きかったが、桂園風の旧派和歌や幼時より教えられた百人一首よりも、良寛や万葉集に親しみを覚え、傾倒してゆく。十八歳で句作を始め、十九歳で「ホトトギス」に入会、子規に会ったのは明治三二年に子規庵を訪ねた一度のみだが、以来、子規の信望者の一人として、活動を広げていくことになる。八一の創作は、同時に短歌へと向かい、明治三五年1月、この春に上京して東京専門学校(早稲田予科)に入学する直前には、 丘の上の梅折りかざしさにづらふ少女のともは若菜つみつつ
人ごとのよごとを繁み久もあはぬ我妹が門の梅咲きにけり けさの朝白梅咲けりけさのあさわれ咲きにきと梅しらめやも
といった、可愛らしい歌を発表している。
二 美術学校生・渡辺文子
どんな作家でも、最も関心を呼ぶのは、その生涯における恋愛談だろう。八一の失恋については有名で、相手の渡辺文子という人は、明治の女性として面白い人なので少し記してみると、この人は八一よりも六歳年下の美術学校生、同級生だった従妹周子を通して、明治三九年、八一が早稲田大学を卒業する頃出会う。 横浜の日本画家の家(「当時珍しかったトマトが食卓にのるような家」だったそうだ)に生まれ、幼少時から絵を描くことを好んだ。十七歳の時に女学校を中退し、本郷菊坂町(一葉が居住していた場所である)にできた女子美術学校洋画科に入学。当時女性に美術の道が開けることは画期的だったという。最初寄宿舎生活を送っていたが、文子の勉学の便のために一家が東京に移住、自宅から通学することになった。周辺には、著名な画家達や漱石、鴎外等の住居があった。卒業後、中村不折(子規庵の正面に居宅があり今は立派な博物館になっている)主催の太平洋画会研究所に入所、同窓には、中村彝、長沼(高村)智恵子らがいた。 男性が多い研究所の中で、都会的で明るい社交的な文子は常にゴシップの種にされた。写真で見るととても綺麗なやさしそうな人で、時の「美人伝」等にも紹介されている。親の勧める縁談を強く拒んで、駆け落ちをするように結婚した三歳年下の洋画家宮崎与平は、「ホトトギス」や「国民新聞」に毎号コマ絵(カット)を描いていた人物。そんな、めくるめく環境の中の華やかな存在だった文子に、八一は二度求婚して二度失敗、にも関わらず、後に文子が「昔なじみ」と語るような、長い親密な付合いを続けることになる。仲間内で、作品の素材として互いを扱っていたともいえるかもしれない。また、文子の家に下宿していた周子(叔父友次郎の娘)は八一の婚約者で、周子が別の男性と恋愛結婚をした時、八一は激怒した、という話があり、先に引用した初期のロマンチックな作品群は、少女期の周子を念頭に詠まれたものであるようだ。プライドを深く傷つけられた八一が、誰が見ても美人で才能豊かな、憧れの対象として申し分ない文子に感情を転嫁し、ある時から強くアプローチをして激情を走らせたとも考えられる。その後の執拗さにはちょっと驚かされるのだが、文子を偶像のような理想的な女神として崇めることで、自らの様々な葛藤の辻褄を合わせてもいたのだろうか。崇拝者がたくさんいた文子にとっても、田舎育ちで地味な空想家の八一の求愛は、さほど重大事ではなかったのだろう。この頃八一は、技巧的ながら率直な恋の歌を、残している。
青丹よし奈良をめぐりて君としも古き仏を見んよしもがも わぎもこをまもれみほとけくさまくら旅なるあれがやすいしぬべく 秋山の色づく見ればその山のそきへに住める妹し思ほゆ 信濃なるあさまが岳に煙立ち燃ゆる心は我妹子の為め いくまきのふみやよめるとことしまた螢とふなりわがまどのもと
三 奈良・いにしへへの旅
ところで、八一が郷里に戻って教職に就いている間に、文子は宮崎与平と結婚してしまう。ひどく落胆した八一は酒浸りになり、傷心のうちに奈良へ美術と歴史研究のための旅をし、徐々に、あのひらがな品詞切りによる分かち書きの、音読みを極力排したやまとことばによる作風をつくりあげていく。 時折八一と比較される高村光太郎は、この頃、広く海外に彫刻修行にでかけ、奈良の古代彫刻を歌に詠み、熱く語っている。廃仏棄釈によって荒れ果て、価値を顧みられずに打ち捨てられかけていた仏像や古美術は、彼らにとって貴重な歴史遺産であったが、もとより万葉の世界に傾倒していた八一である。眼前に、その生きた三次元の世界が顕現した時の感動は、大きかったろう。 かすがの に おしてる つき の ほがらかに あきの ゆふべ と なり に ける かも くわんおん の しろき ひたひ に やうらく の かげ うごかして かぜ わたる みゆ わぎもこ が きぬかけやなぎ み まく ほり いけを めぐりぬ かさ さし ながら いかるが の さと の をとめ は よもすがら きぬはた おれり あき ちかみ かも あせたる を ひと は よし とふ びんぶくわ の ほとけ の くち は もゆ べき もの を
八一は古代への憧憬を細かに分析し、知っている時代に滅びたものを懐かしむのと知らない時代のものを懐かしむのとは違う、と述べているが、確かに、同じ時代にその空間を共有していたかどうかでその印象や受けとめ方は大きく違う。もし八一が自身の知っている時代を懐かしむことがあったとしたら、それはあるいは、天保年間から隆盛を誇り、八一幼年の頃まで公の遊廓でもあったという生家の料亭の周辺の文化であったかもしれない。
さて、宮崎与平という人は、二十四歳で結核のため夭逝してしまうのだが、その画風は与平式と呼ばれ、竹久夢二が展覧会で与平の作品を見て、自分もこのような絵を描こうと決意した、という逸話が残されている。実際、与平が文子を描いた「ネルの着物」「帯」のような画は、夢二が柳原白蓮を描いたものと言っても知らない人には通じると思われるような魅力的な作品なのだが、その絵について八一は、「肖像に過ぎず」とあからさまに面白くなさそうである。失恋の逆恨みや嫉妬も大きいかもしれないが、八一は、あれほど古美術を愛し探究を深めていながら、意外にも永遠なる芸術作品より現実の生命を重んじているのだ。好んで歌材とした鹿についても、
「鹿は生きてゐるから誰の目にも面白くて簡単で安心だ、美術も生きてゐるし、高尚なものには違ひなからうが、それを活かして見るのは、目のはたらき一つであるからむつかしい」「(鹿の)鳴き声は大ッぴらで、高ッ調子で、そのまま人の心に強く沁み入る、あんな調子で人間の歌も詠めないものであろうか」と述べている。それは、「銅とスズとの合金が立つてゐる/いさぎよい非情の金属が青くさびて地上に割れてくづれるまで/立つなら幾千年でも黙つて立つてろ。」と書いた高村光太郎が「彫刻の安全弁としての詩」という言葉で語ったことと同義なのだろうか? かすがの の みくさ をり しき ふす しか の つの さへ さやに てる つくよ かも こがくれて あらそふ らしき さをしか の つの の ひびき によ は くだち つつ
月に照らされる闘争的な鹿の角は、いさぎよい合金の金属の、非情な響きや輝きは湛えてはいないようである。
岡井隆は「その様式的にすぎるアルカイズム(擬古主義)に慣れ親しむのはなかなか骨が折れる」としながら、「八一の仏像の歌の底には、現実の女人への嫌忌があり不信があったとおもえば、よく理解できる」と述べている。様式美の裏には、生々しい現実がいつも存在しているが、時代の象徴として作られた仏像彫刻に、さらに理想化した女性像を重ねるのだから、単なる現実逃避ではないさらに錯綜した美意識が結晶されているのだろう。 ふぢはら の おほき きさき を うつしみ に あひみる ごとく あかき くちびる からふろ の ゆげ の おぼろ に ししむら を ひと に すはせし ほとけ あやしも みほとけ の ひぢ まろら なる やははだ の あせむす まで に しげる やま かな
これら仏像の歌のなまめかしさについては、人からもかなり言われたようで、後に八一は、「そもそもこれが會津のエロだ、と云ふものがあるが、そうとばかり片づけられない。美術史上、際立つて特色の強かつたその時代の、官能的な持ち味が滲み出して、ついこんな歌になつたのであり、平安初期の妖婉な肉感に着目したとしてもただ私だけのせゐにして特別の見つけものをしたやうな物の云ひ方をしてゐる」と微笑ましい異議を申し立てている。
四 ひらがな分かち書きの謎
八一が、最終的にひらがなだけの品詞による分かち書きという形を選んだのはなぜなのだろうか。自他ともに気難しいと認める八一が、もし同時代の歌人と交流を深め、普通の歌の作り方を(その表記だけでも)していたら、現在これほどマイナーな歌人として扱われることはなかっただろう。 いにしへ に わが こふ らく を かうべ に こ おほさか に こ と しづこころ なき
これは、再婚後の文子に神戸や大阪の自宅に招かれたことに対する心情を詠んだ歌なのだ...