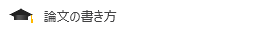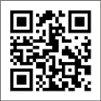資料紹介
「倫教塔」夏目漱石ーその一度の空想と現実ー
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
本書の出だしで、漱石は、「まるで御殿場の兎が急に日本橋の真中へ抛り出されたような心持ちであった。表へ出れば人の波にさらわれるかと思い、家に帰れば汽車が自分の部屋に衝突しはせぬかと疑い、朝夕安き心はなかった。この響き、この群集の中に二年住んでいたら吾が神経の繊維もついには鍋の中の麩海苔のごとくべとべとになるだろうとマクス・ノルダウの退化論を今さらのごとく大真理と思う折さえあった。」と記しているから、当時の倫敦は漱石が生まれ育った東京以上の大都市だったのであろう。
また、漱石が自分を「御殿場(ごてんば)の兎(うさぎ)」と表わして、江戸から明治に激変した日本が世界の中に投げ出され彷徨っている様子と、漱石が倫敦の中を彷徨っていることを重ね合わせ、当時の日本の姿は倫敦にいる漱石の姿でもあったのであろう。
そして、「無論汽車へは乗らない、馬車へも乗れない、滅多な交通機関を利用しようとすると、どこへ連れて行かれるか分らない。この広い倫敦を蜘蛛手十字に往来する汽車も馬車も電気鉄道も鋼条鉄道も余には何らの便宜をも与える事が出来なかった。」とのことから、交通網の発達していたことが分かる。
漱石が,「着後...
販売者情報
上記の情報や掲載内容の真実性についてはハッピーキャンパスでは保証しておらず、
該当する情報及び掲載内容の著作権、また、その他の法的責任は販売者にあります。
上記の情報や掲載内容の違法利用、無断転載・配布は禁止されています。
著作権の侵害、名誉毀損などを発見された場合はヘルプ宛にご連絡ください。