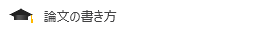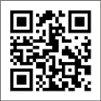資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
『学歴社会とは何かを明らかにし、高学歴化が進行すると教育はどのように変化するのかについて学力の視点から述べよ』
学歴社会とは、当該社会の社会的・職業的地位を決める主たる基準の一つが学歴であるような社会を指す。社会的地位とは職業的地位と重なる側面もあるが、もっと広い意味であり、具体的には文化的地位なども含む。しかし、この学歴社会に対しては、古くから様々な批判がなされてきた。就職・昇進や結婚と関連した大学間格差の存在や、学歴による差別はその代表的なものである。また、学校の管理・教育のあり方や学校外の教育産業に対する批判も数多く見られる。ただし、今日のような学歴社会になるにはそれなりの歴史と必然性がある。明治時代がスタートとし、維新政府が必要としたのは、各分野における優れた人材であり、その資質・量的に安定した供給を保証してくれる機構であった。それまでの身分社会では、主として士農工商のような封建制度下において、父の身分が子どもの進路・職業を決定した。教育においても典型的にいえば、氏族の子どもは藩校に行き、四書五行や朱子学など人の上に立つ者として必要な知識を、町人・農民の子どもは寺子屋に行き、読み・書き・そろばんなど実用的な知識・技能を教えられていた。しかし、このシステムは明治維新期には適さなかった。「富国強兵」のスローガンの元、幅広い分野で相当数のリーダーが必要とされ、しかもリーダーに求められる知識・技術の水準は絶えず向上した。これまでの身分に依存したシステムでは効率の良い人材育成の望めず、したがって、この必要性を満たすものとして当時考えられたのが、学歴社会や学歴主義であった。学校という場にできるだけ広い諸階層の子どもを集め、そこで一定のルールに基づき子どもを競わせる。そして、学校という場でのパフォーマンスに応じて社会的・職業的地位を割り振るという流れが誕生したのである。学歴社会は、一方では国民の精神的、知的統合や識字率の向上など文化的基盤を整備する役割を果たし、他方では多面的にわたるリーダーを質量とともに安定的に供給する役割を果たした。つまり、近代日本をそれなりに支えてきたメカニズムだったのである。
学歴社会とよく混同される言葉に「高学歴社会」がある。これは単に「高学歴社が多い社会」を意味する単語で、具体的には、高校卒業後の高等教育機関への進学率が50%を超える社会であることを意味する。日本はアメリカ合衆国・カナダなどと並び、数少ない高学歴社会の一つである。ここに至るまでの歴史は、先述した通り明治時代にさかのぼる。しかし、戦前に上級学校へ進学できるものは、経済的に恵まれていたり、一部の学問によって身を立てようと考えるものに限られていた。つまり、学歴がなくても社会で成功できる可能性は多く存在していた。ところが、戦後、民主主義の時代になり、個人の努力と能力によって成功の機会が平等に与えられるように、教育の重要性が強調されてきた。今まで学歴社会に参加しなかった階層の者が参入してきたが、やはり、経済的に恵まれていなければ大学まで行くことは難しかった。また、社会も多くの優秀な人材を必要としていて、需要が供給を大きく上回っていたので、高学歴は社会的な成功を約束していた。この頃は、学生たちも大いに勉強したので、学歴=実力と言うことができる。
高度経済成長期に入り、国民は経済的に豊かになってきた。すると、学歴獲得レースに参加する者が急速に増えてきた。高学歴を獲得するための受験競争は過熱化し、学歴が社会的成功のためのパスポートになる。ほとんどすべての子供が学歴獲得のレースに参加するようになった。多くの人が学歴獲得レースに参加するようになると、そのゴールがさらに遠くなる。とりあえずは高校進学がゴールであったが、それがある程度達成されると、今度は大学進学がゴールになる。それもある程度達成されると、どの大学に進学するかがゴールになる。本来は、学校で勉強をして学力を身につけることによって社会的成功を実現してきた。しかし、学歴社会が成熟してくると、どの学校に所属するかということが社会的成功の正否を決定するようになる。また、学歴獲得のシステムも研究されるようになり、ゴールを目指してより効率的な方法が開発される。しかし、その精度が高くなればなるほど、受験に必要な学力と社会で必要な実力の乖離が大きくなった。やがて、供給が需要を上回ると、学歴が必ずしも社会的成功と一対一でなくなってくる。まして、受験のための学力はあるが社会で必要な実力を身につけていない、ゴールインするとなると、学歴の価値が形骸化するのは当然といえる。しかし、学歴の相対的価値の低下にもかかわらず、日本の受験競争は沈静化しない。その要因として次のようなことが考えられる。
①惰性…「みんながいくから自分も行く」といった惰性によって進学が行われる。
②タイムラグ…教育の機会に恵まれず下積みで苦労した親たちが、「自分の子どもにだけは」と願って、子どもたちを進学させる。
③エントリー…大学の卒業資格だけでは成功へのチケットを手にすることはできないことはわかっているが、高学歴・経済低成長の時代になっても排除されないために、とりあえず大学卒の資格だけは身につけておく必要がある。
④社会的圧力…進学率が高度に高まると、進学しない者にはなんらかの欠陥があるとみなされがちなために、不本意ながら就学する。
⑤能力証明…進学競争への参加者の増加の中で、より格付けの高い学歴を手にいれることによって自分の能力を証明しようとする。
⑥企業論理…供給側の論理として、学校経営を維持するために子供の確保が必要になる。私立は勿論、公立も税金で運営されている以上同じ課題を抱えている。
学歴獲得システムの精度が高くなるにつれて、それを始動させる時期は早くなる。競争は低年齢化する。また、多くの子供が同じレースに参加しようとする。幼い頃から、社会で必要でない学力の獲得に全力を尽くす。最後までこの競争に参加した場合、それまでの多くの時間を空費することになる。しかし、その時期に獲得すべき様々な<能力>を獲得しないまま成長する。それでも、競争に勝利した場合は、学歴を獲得できるかもしれないが、敗北した場合は、学歴を獲得できないだけでなく、自信も失う。すべての<能力>を否定されたような錯覚に陥る。途中で競争から降りた場合は、その時点での篩に掛けられて脱落したならば、敗北感を味わうことになる。その敗北にこだわり続けたり、レールに未練を残していたりすると、その後の人生においても意欲が湧かない。その時点で、価値観の変換に成功した場合は、その後の人生において新たな意欲を見い出すことができる。
現実として、それまでの段階で敗北体験をして高校に入学してきた生徒は、敗北感を引きずっており、無気力状態に陥ることが多い。また、この現象は現代の大学生にも当てはまる。社会の発展期においては、供給源である大学が少なかった時代の学生は、自分たちが社会をなんとかしなければという使命感に燃えていた。しかし、人材の供給源が拡大するようになると、学生の使命感は低下してくる。社会で何をしたいかという目的から、どの大学に入るかということ自体が目的になってきた。自分が何をしたいのかわからないという学生が急増している。また、受験や大学で身につけた学力と、社会が要求する高度な専門的な力の差が大きいために、社会で期待していた地位を占める機会を与えられない場合が多くなっている。
このように、名実共に高学歴社会となった日本ではあるが、そこには必ずしも学力が添付されていない現実がある。<教育>内容として培われる学力は確かに存在するが、社会がその学力を求めているかは別の話になってしまうのである。幼稚園受験という単語も珍しくなくなった今日日、教育者側も教育内容の充実に必死である。良い学校に進む為、良い会社に就職する為、それ相応の教育は行われる。しかし、あくまで学力は学力に過ぎない。本来、教育はより広いものであり、家庭におけるしつけや地域社会における学習など、学校外で学ぶことの方が多いともいえる。現代社会では、あたかも公教育=教育の全てと錯覚されがちであり、子どもの教育をすべての学校に任せる(学校の役割の肥大化)というアンバランスを呼んでいる。これもまた、現代社会における教育の問題点の1つであり、学歴社会を見つめ直す大きな要素である。
<参考文献>
岩田龍子『学歴主義の構造』 日本評論社
刈谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』 中公新書
原清治『教育の比較社会学』 学文社