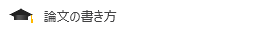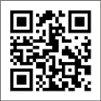資料紹介
講義「 国際関係論 」の中盤で出された課題が、この書評レポートでした。
書評では、戦死者数の定義について疑問を提起しています。
本書を読む前から抱いていた、自分なりの「戦死者数」という概念に対する違和感をまとめたような内容です。
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
『現代国際関係学―歴史・思想・理論』書評
国際関係学を学ぶ上で欠かせない国際社会の歴史、思想、理論などの基本的なことが網羅的に書かれている本書は、各章の冒頭に国際社会の歴史年表にあわせ、その時代ごとに生み出されてきた思想や理論が書かれている。国際関係学の誕生に大きな影響を与えてきた思想家とその思想の変遷からは、現在の国際関係学の理論の根幹がどのような歴史的背景のもとに構成されてきたのかがよくわかるようになっている。また、国際関係学の大きな思想の源流ともいえる、リアリズムとリベラリズム。その2大潮流の変遷と、そこから派生して生まれた思想や影響を受けた思想の流れもわかりやすく書かれている。
非常にわかりやすく国際関係学の基本事項が押さえられている本書だが、1つ気になるのは、17章の 表Ⅶ2 冷戦後の紛争データ(1989-99)である。表の内容自体には直接関係のない話になるが、注(2)で「『戦争』とは年間1000人以上の戦闘関連死者を出した『大規模武力紛争』をいう。年間25人以上、累積1000人以上の戦闘関連死者を出したものを『中規模武力紛争』、年間25人以下、累積1000人以下の戦闘関連死者を出したものを「小規模武力紛争」と各定義する。」(P.256)とある。戦争や紛争の規模を死者数で定義すること自体は今さら珍しいことではないかもしれない。しかし、本書の様々な箇所でも書かれているが、国際社会の歴史とは、先進国側が自分たちの論理を一方的に途上国側に押し付けてきた側面が多々あった歴史でもある。この注を読んだときに改めて思い浮かんだのは、死者数で紛争を定義するということには、先進国側の途上国側に対する一方的な見方とどことなく近いニュアンスが感じられるということである。学問研究における資料として、戦争や紛争をその規模などでどこかで線引きしなければならないのはわかる。たしかにその線引きの基準として一番明確なのは死者数かもしれない。戦争や紛争の規模を計る上で死者数のデータは、マスメディアなどでも戦争のインパクトを一番わかりやすく伝えるデータとして一般的に使われている。それでも、死者数という基準でしか戦争や紛争の規模を説明できないというのは、やはり無機質な印象を強く受ける。それは時に、人の命を数字で計ることで戦争や紛争の持つ本質的な重みを見過ごしてしまっている様な印象を与える。
では、死者数に代わる線引きの定義は見当たるのかというと、中々見当たらない。しかし、戦争を人の数で計る以外の基準はないのかどうか考えていくのも国際関係学の役割ではないだろうか。少々極端にいえば、これは先進国と途上国の力量関係を扱う国際関係学という学問分野の倫理観に関係してくる事柄だと思うのだ。国際社会の歴史における先進国の途上国に対する様々な搾取などは、地球温暖化問題を巡る京都メカニズムなどで「公共財に市場メカニズムを導入し(空気までもカネで売買する)先進国中心の国家エゴイズムに依拠する限り、地球環境保全は幻想に終わらざるをえないのかもしれない。」(P.359)というように、現在でも形は変わりながらも傲慢な姿勢として未だに残っているのである。この先進国のご都合主義を途上国の視点も考慮しながら改めていくことは、これからの国際関係学の大きなテーマの1つと言えるだろう。つまり、先進国の途上国に対する姿勢を注視し、時に発想の転換を促すような役割が国際関係学には求められていくと思われる。その際に国際関係学は、この学問が生まれるときに描いた、いかに戦争を防ぐのかという崇高な理想の倫理観を持ち続けていなくてはならないだろう。死者数で戦争や紛争を定義する資料や記述は世の中にあふれており、この本書に限った話ではないが、先進国側の途上国側に対する傲慢な姿勢が現在もなお続いていることを指摘する記述がみられる本書だからこそ、戦争や紛争を死者数で定義しようとする方法に代わる方法を見出すべきではないかということを考えさせられる。
< 参考文献 >
『現代国際関係学―歴史・思想・理論』 進藤榮一 2001年 有斐閣