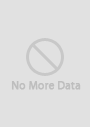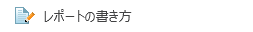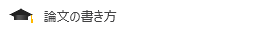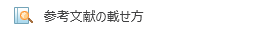資料紹介
医師Aは患者甲を殺したいほど憎んでいたが、某日、甲殺害の故意で看護師Bに毒薬入りの注射器を手渡し、甲への注射を依頼した。ところが、Bは、それが毒薬入りの注射器であることを見破り、自らも甲を憎んでいたので、これを奇貨として、殺意をもって甲に注射し甲を死亡させた。A、Bの刑事責任について論ぜよ。
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
他人を道具として利用することによって構成要件に該当する行為を行うことを間接正犯といい、自己の犯罪として単独で実行行為を行う犯罪形態で、単独正犯に含まれる。また、他人を教唆して犯罪を実行するに至らしめた者を教唆犯といい(刑法61条)、他人の犯罪に加担するに過ぎず、共同正犯とは異なる。
医師Aは、患者甲殺害の故意で看護師Bに毒薬入り注射器を手渡し、Bが甲に注射し死亡させたことから、Aの行為は主観的には故意のない者を利用した間接正犯の問題となるが、その後、Bはそれが毒薬入り注射器であることを看やぶった上で殺意をもって甲に注射し、客観的には教唆犯にもあたることから、教唆犯と間接正犯の錯誤が問題となる。
そもそも間接正犯は、直接正犯と共犯の間に存在する処罰の隙間を埋めるための概念とされ、正犯者の構成要件・違法性・有責性の有無等によって教唆犯の範囲を区別し、不成立の場合に間接正犯が成立すると解した。また、被利用者がどのような状態であるかによって判断に差異がある(行為能力のない者、故意のない者等)。従来の通説・判例は、構成要件に該当しかつ違法・有責であることを要する極端従属性説を採用していたが...