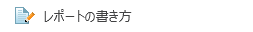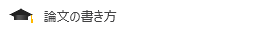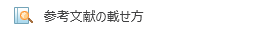資料紹介
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
入門講義 少年法
➣審判過程
・審判の開始と不開始
審判(=刑事事件でいうところの公判)は受理後必ずしも行われるわけではない
家裁が調査の結果、審判を開始するのが相当と認めたとき(少§21)
⇒審判を開始するのに必要な要件が存在
1.審判条件が存在すること(≒訴訟条件)
①日本に裁判権があること(≒刑訴338条4号)
②当該家庭三番所が管轄権を持つこと
③少年が生存していること(≒339条①4号)
④対象者が20歳未満 ←犯罪事件は検察に送致される⇒不存在≠審判不開始
⑤有効な送致・通告・報告が存在すること(≒338条4号)
⑥当該事件につき少年法46条が規定する一事不再理効がない(≒337条1号)
⇒②については、刑事事件の場合、管轄外は原則手続打ち切りであるが、少年法の目的である保護の観点から、形式的な瑕疵を理由に手続を終了させてしまうのは望ましくない→管轄家裁への移送が義務
◎事件の二重係属について
刑事手続:後の公訴が棄却(338条3号・339条①5号)
∵被告人に無用な応訴の負担を...