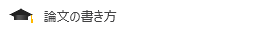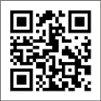資料紹介
正準変換
座標変換の一般化。
ここまでが基礎だ
これから正準変換の説明を始めることにしよう。 本当は第1部の「基礎の基礎」の中の仕上げとして入れるつもりだったのだが、これを理解するための自然な流れとして変分原理を知っておくのが良いと思い、このような順序で説明することになった。 よって、私の見方で行けば、ここまでが解析力学の「基礎」である。 まぁ、このサイト全体が基礎レベルなのでようやく「基礎の基礎」ってとこだ。
しかし偉そうなことは言うまい。 私が学生の頃にはここまで理解できていなかった。 しかも、そこらの難しい書き方をしている教科書には未だに手が出せないでいる。 ああ、なんとレベルの低い情けない話だろう。 もっともっと上があるのだ。 まぁ、そんな事が言えるくらいのところまで来れたことは素直に喜ぶべきだろうか。
正準変換とは何か?
ラグランジュ方程式は座標変換に対して不変であった。 そしてハミルトンの正準方程式もそうである。 ところで、ハミルトン形式では座標と運動量は対等な立場の変数として論じられるのであった。 それであるのに「座標変換」しかないのはどういうわけだ、不自然じゃないか、というのである。 全く無茶なことを言ってくれる。 しかし、学問というのは一見無茶に見える要求に何とか応えようとして発展してきたものであるようだ。
この辺りの事情をもう少し詳しく話そう。 座標変換によって座標 q が新しい座標 Q で書き表されるとする。 この時、 q と Q の間には1対1の対応が成り立っていなくてはならない。 つまり Q は qi の関数として表される。
q → Q( q1, q2, .... q3N )
一方、座標が変換されれば、当然それに応じて運動量も変換を受けることになるだろう。 しかし、新しい運動量は元の運動量の関数にもなっているはずだ。
p → P( q1, q2, .... q3N, p1, p2, .... p3N )
新座標は旧座標だけの関数なのに、新運動量は旧座標と旧運動量の関数になっている。 この辺りのアンバランスが気に入らないのである。 いっそのこと、新座標も旧運動量によって決まるような一般的な変換を考えてはどうだろうということになる。
q → P( q1, q2, .... q3N, p1, p2, .... p3N ) p → Q( q1, q2, .... q3N, p1, p2, .... p3N )
こうすれば座標と運動量は本当に対等の立場に立てることになるではないか。 もうメチャクチャである。 座標が運動量で決まるなんて、相対性理論を思い浮かべるような話だ。 実は相対性理論というのは解析力学をお手本にしたふしがあるのだが。
このような形のあらゆる変換を認めてしまえば、せっかくの正準形式の理論が使えなくなってしまう可能性が出てくる。 そこで一つだけ次のような条件を課することにしよう。
「変換してもハミルトンの正準方程式の形式が成り立つこと」
そのような変換を「正準変換」と呼ぶことにする。
この定義によれば、全ての「座標変換」は正準変換の一部として含まれることになる。 つまりこれからやろうとしているのは、「座標変換」をもっと広い意味を持つ「正準変換」に拡張するという作業なのである。
変分原理の応用
( p, q ) 系を ( P, Q ) 系に変換してもハミルトンの正準方程式が成り立つということは、変換後の新しいハミルトニアンを K として、
が成り立つということであ
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
正準変換
座標変換の一般化。
ここまでが基礎だ
これから正準変換の説明を始めることにしよう。 本当は第1部の「基礎の基礎」の中の仕上げとして入れるつもりだったのだが、これを理解するための自然な流れとして変分原理を知っておくのが良いと思い、このような順序で説明することになった。 よって、私の見方で行けば、ここまでが解析力学の「基礎」である。 まぁ、このサイト全体が基礎レベルなのでようやく「基礎の基礎」ってとこだ。
しかし偉そうなことは言うまい。 私が学生の頃にはここまで理解できていなかった。 しかも、そこらの難しい書き方をしている教科書には未だに手が出せないでいる。 ああ、なんとレベルの低い情けない話だろう。 もっともっと上があるのだ。 まぁ、そんな事が言えるくらいのところまで来れたことは素直に喜ぶべきだろうか。
正準変換とは何か?
ラグランジュ方程式は座標変換に対して不変であった。 そしてハミルトンの正準方程式もそうである。 ところで、ハミルトン形式では座標と運動量は対等な立場の変数として論じられるのであった。 それであるのに「座標変換」しかないのはどういうわけだ、不自然じゃないか、というのである。 全く無茶なことを言ってくれる。 しかし、学問というのは一見無茶に見える要求に何とか応えようとして発展してきたものであるようだ。
この辺りの事情をもう少し詳しく話そう。 座標変換によって座標 q が新しい座標 Q で書き表されるとする。 この時、 q と Q の間には1対1の対応が成り立っていなくてはならない。 つまり Q は qi の関数として表される。
q → Q( q1, q2, .... q3N )
一方、座標が変換されれば、当然それに応じて運動量も変換を受けることになるだろう。 しかし、新しい運動量は元の運動量の関数にもなっているはずだ。
p → P( q1, q2, .... q3N, p1, p2, .... p3N )
新座標は旧座標だけの関数なのに、新運動量は旧座標と旧運動量の関数になっている。 この辺りのアンバランスが気に入らないのである。 いっそのこと、新座標も旧運動量によって決まるような一般的な変換を考えてはどうだろうということになる。
q → P( q1, q2, .... q3N, p1, p2, .... p3N ) p → Q( q1, q2, .... q3N, p1, p2, .... p3N )
こうすれば座標と運動量は本当に対等の立場に立てることになるではないか。 もうメチャクチャである。 座標が運動量で決まるなんて、相対性理論を思い浮かべるような話だ。 実は相対性理論というのは解析力学をお手本にしたふしがあるのだが。
このような形のあらゆる変換を認めてしまえば、せっかくの正準形式の理論が使えなくなってしまう可能性が出てくる。 そこで一つだけ次のような条件を課することにしよう。
「変換してもハミルトンの正準方程式の形式が成り立つこと」
そのような変換を「正準変換」と呼ぶことにする。
この定義によれば、全ての「座標変換」は正準変換の一部として含まれることになる。 つまりこれからやろうとしているのは、「座標変換」をもっと広い意味を持つ「正準変換」に拡張するという作業なのである。
変分原理の応用
( p, q ) 系を ( P, Q ) 系に変換してもハミルトンの正準方程式が成り立つということは、変換後の新しいハミルトニアンを K として、
が成り立つということである。 そのためには、
と置いた場合に、δI = 0 が成り立っていればいい。 前回の説明はこれを言うために必要だったのである。 さて、これを成り立たせるためにはどうしたらいいだろうか?
もともと
と置いたときに δI = 0 になっているわけだから、以上を総合すると、任意の定数 λ を使って
と表すことが出来る。 こうすることで、( P, Q ) 系が正準形式を実現する条件を保ったまま、 ( p, q ) 系 と ( P, Q ) 系 の間の関係を導くことが出来るわけだ。 2つの項の差を取っているのはこの後で導かれる結果を分かりやすい形にするための技巧でしかない。 この式が成り立つ条件は、
である。 ここで W1 というのは ( q, Q, t ) を変数とする任意関数である。 これでうまくいく理由は、これを一つ前の式に代入してみれば分かる。 積分の結果は初期状態と終状態の ( q, Q, t ) によって決まる定数になっており、そこでは δq = 0, δQ = 0 であるからその変分を取ったものは0になるという理屈だ。
ここで W1 を ( q, Q, t ) の関数であるとしたのはこの後の計算をするのに都合が良いからである。 変数が他の組み合わせになる場合についてはもう少し後で計算することになる。 だからとりあえず W の添え字に1を付けて区別しているのである。
もう一つ補足しておこう。 ここでなるべく一般的な議論をしようと思って定数 λ を使っているが、計算がややこしくなるので今後は λ = 1 の場合のみを考えることにする。 これで議論の一般性が損なわれるのではないかと心配する必要はない。 なぜなら、a b = λ となるような2つの定数を使って、P を a 倍、Q を b 倍、 K を a b 倍してやれば λ ≠ 1 の場合を計算したのと同じになるではないか。 座標や運動量やハミルトニアンのスケールは後で好きにいじってやって構わないというわけだ。 実際に大抵の教科書では、λ = 1 として計算したものを「正準変換」と呼んでいる。
変換の母関数
よって、正準変換が成り立つ条件は、
である。 この両辺に dt を掛けてやれば、
となる。 ここで W の全微分の式、
(この式は微積分から当然言える内容である)を持ち出して一つ上の式と係数比較してみよう。 次の 6N + 1 個の関係式が得られるはずである。
さあ、この式さえあれば正準変換を実行できることになる。 なぜなら、W1 は ( q, Q, t ) の関数なので、第1の式から p が ( q, Q, t ) の関数として求められるだろう。 これを Q について逆に解いてやれば欲しかった変換の式が Q ( q, p, t ) の形で求められる。 さらに2番目の式から P ( q, Q, t ) が求まるが、この変数 Q に先ほどの形を代入してやれば、P ( q, p, t ) となるではないか。 そして3番目の式からは新しいハミルトニアンが計算できるが、これを新しい変数 ( P, Q, t ) で表してやればいいのである。
このように一つの関数 W1 が決まると変換が一つ決まることになる。 こういうわけでこの関数を「変換を生み出す関数」という意味を込めて「母関数」と呼ぶのである。
母関数のルジャンドル変換
ここまでは母関数として、独立変数が ( q, Q, t ) である場合の W1 を使ってきた。 では独立変数が別の組み合わせになる場合はどのようになるのだろうか? 独立変数を入れ替えるための便利な手法があったことを思い出そう。 そう、ここで再びルジャンドル変換を使うのである。 例えば、独立変数が ( p, Q, t ) である関数 W2 を作るためには、 W1 の変数である q を p に入れ替えてやればいいので、
としてやればいい。 こうすれば、W2 の全微分は
となる。 よって、先ほどと同じように全微分の形式を書いて係数比較してやることで次の関係式が得られる事になる。
全ての場合を説明する必要はもうないだろう。 全く同じ処方で ( q, P, t ) の関数 W3 を使う場合も計算できる。 これは W1 の Q を P に入れ替えてやればいい。 結果はこうなる。
( p, P, t ) の関数 W4 について計算する場合には、 W1 の Q を P に、q を p に入れ替えてやる必要があるので、
と置けばいい。 結果は次のようになる。
実例は今度ね
ここで代表的な4通りの母関数についての関係式を求めたが、この理屈が理解できていれば変数が入り混じっている場合についても計算できるだろう。 また、この4つの場合の関係式を丸暗記する必要もなくてパターンさえつかめば実に単純だ。 いつでも簡単に思い出せるだろう。
しかし原理が分かっても実例がなければイメージが描きにくいだろうから、次回はこの変換を使った実例を紹介することにしよう。
資料提供先→ http://homepage2.nifty.com/eman/analytic/canonical.html