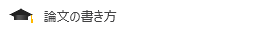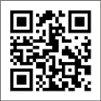資料紹介
原子の構造
原子の存在は、風のようなものだ。
原子模型
電子は負の電荷を持っており、原子核の持つ正電荷に引き寄せられることで、原子核の周囲を回っているらしい。 その事が確からしいと分かり始めたのは1911年のラザフォードの実験による。
しかしなぜ電子が原子核に突っ込まないで軌道を保っていられるのかは長い間の謎であった。 というのも、電荷を持った粒子が加速運動を行うと、電磁波を放出しながらブレーキが掛けられるという良く知られた現象があるからである。 原子核の周りでの円運動も加速運動の一種であるから、電子は光を放出してその分の運動エネルギーを失い、原子核の引力に負けてたちまちの内に原子核に墜落してゆくはずなのだ。 電磁気学の計算からは確かにそうなることが導かれる。
なぜ電子は電磁波を放出しないで安定な状態を保っていられるのだろう。 そしてどんな軌道を回っているのだろう。 その仕組みは量子力学によってようやく理解できるようになった。
基本となる式
原子核の電荷によるポテンシャルエネルギーは
と書ける。 ごちゃごちゃとした係数をひとまとめにして a と置いたわけだが、念のために書いておけば、
である。 Z は原子番号で、e は電子の電荷を表す。
これをシュレーディンガー方程式に代入して解けば、電子が原子核の周りでどんな波を作るのかが分かるはずだ。 このポテンシャルの式は原子核からの距離 r にのみ依存する球対称の形をしているので、今までの式では解きにくい。 時間に依存しない3次元のシュレーディンガー方程式
を極座標に変換してやろう。 これは解析力学のページに書いておいた「座標変換のやり方」を参考にしてこつこつやれば出来る。
これで本当に解きやすくなったのかと疑いたくなる気持ちは分かる。 両辺に r2 を掛けたり、移項したりすれば少しは見やすくなるかも知れない。
それでもまだ、r やら θ やら やらが一緒になっていて、解きにくいどころか、どこから手を付けたらいいか分からない状態なので、前に紹介した変数分離法を使って分解してやることにする。 変数分離法というのはこんな具合にいつでも気軽に使うようなテクニックなのである。
変数分離法
やることは前に行ったのと大して変わらない。 まず波動関数が、
という形になっていると仮定してやる。 すると方程式は
と書けるだろう。 微分に関係のない関数は定数のように扱って各項の前の方へ出しておいた。 この式の両辺を R ( r ) Y ( θ, )で割ってやると、
のようになって、左辺は r のみの関数に、右辺は ( θ, ) の関数にすることが出来る。 つまり、両辺は r, θ, に依存しないある定数になっているはずだ。 それを λ と置こう。 そうすれば、上の式を次のような二つの式に分離する事が出来る。
次に、今、分離したばかりの2番目の式に含まれる θ と を分離してやりたい。 その準備としてこの両辺に sin2θ を掛けて少しすっきりさせておこう。
ここで、
を仮定して代入してやると、
となる。 やはり同じように両辺を で割ってやる。
するとこの式の左辺は θ のみの関数であり、右辺は のみの関数となるので、両辺は θ にも にも依存しないある定数 ν に等しいに違いない。 こうして2つの式に分離できることになる。 ついでだから、先ほどの結果とまとめて書いておくことにしよう。
結局、極座標のシュレーディンガー方程式は、次のような3つの式に分離できたことに
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
原子の構造
原子の存在は、風のようなものだ。
原子模型
電子は負の電荷を持っており、原子核の持つ正電荷に引き寄せられることで、原子核の周囲を回っているらしい。 その事が確からしいと分かり始めたのは1911年のラザフォードの実験による。
しかしなぜ電子が原子核に突っ込まないで軌道を保っていられるのかは長い間の謎であった。 というのも、電荷を持った粒子が加速運動を行うと、電磁波を放出しながらブレーキが掛けられるという良く知られた現象があるからである。 原子核の周りでの円運動も加速運動の一種であるから、電子は光を放出してその分の運動エネルギーを失い、原子核の引力に負けてたちまちの内に原子核に墜落してゆくはずなのだ。 電磁気学の計算からは確かにそうなることが導かれる。
なぜ電子は電磁波を放出しないで安定な状態を保っていられるのだろう。 そしてどんな軌道を回っているのだろう。 その仕組みは量子力学によってようやく理解できるようになった。
基本となる式
原子核の電荷によるポテンシャルエネルギーは
と書ける。 ごちゃごちゃとした係数をひとまとめにして a と置いたわけだが、念のために書いておけば、
である。 Z は原子番号で、e は電子の電荷を表す。
これをシュレーディンガー方程式に代入して解けば、電子が原子核の周りでどんな波を作るのかが分かるはずだ。 このポテンシャルの式は原子核からの距離 r にのみ依存する球対称の形をしているので、今までの式では解きにくい。 時間に依存しない3次元のシュレーディンガー方程式
を極座標に変換してやろう。 これは解析力学のページに書いておいた「座標変換のやり方」を参考にしてこつこつやれば出来る。
これで本当に解きやすくなったのかと疑いたくなる気持ちは分かる。 両辺に r2 を掛けたり、移項したりすれば少しは見やすくなるかも知れない。
それでもまだ、r やら θ やら やらが一緒になっていて、解きにくいどころか、どこから手を付けたらいいか分からない状態なので、前に紹介した変数分離法を使って分解してやることにする。 変数分離法というのはこんな具合にいつでも気軽に使うようなテクニックなのである。
変数分離法
やることは前に行ったのと大して変わらない。 まず波動関数が、
という形になっていると仮定してやる。 すると方程式は
と書けるだろう。 微分に関係のない関数は定数のように扱って各項の前の方へ出しておいた。 この式の両辺を R ( r ) Y ( θ, )で割ってやると、
のようになって、左辺は r のみの関数に、右辺は ( θ, ) の関数にすることが出来る。 つまり、両辺は r, θ, に依存しないある定数になっているはずだ。 それを λ と置こう。 そうすれば、上の式を次のような二つの式に分離する事が出来る。
次に、今、分離したばかりの2番目の式に含まれる θ と を分離してやりたい。 その準備としてこの両辺に sin2θ を掛けて少しすっきりさせておこう。
ここで、
を仮定して代入してやると、
となる。 やはり同じように両辺を で割ってやる。
するとこの式の左辺は θ のみの関数であり、右辺は のみの関数となるので、両辺は θ にも にも依存しないある定数 ν に等しいに違いない。 こうして2つの式に分離できることになる。 ついでだから、先ほどの結果とまとめて書いておくことにしよう。
結局、極座標のシュレーディンガー方程式は、次のような3つの式に分離できたことになる。
いきなり3つの式に分離することはできなくて、2つずつ分けてゆく必要があるところが少し面倒なのだが、手間が掛かる分だけ愛着も増すというものだ。
方向の依存性
まずは最も簡単そうな3番目の式から解いてみよう。
という解があることはすぐに分かる。 他にも、元の方程式の ν が 0 の時には、
という解もある。
ところで の範囲は 0 ≦ < 2π であって、原子核の周りをぐるっと一周して元の位置に戻ったときに波動関数が同じ値になっていないとおかしいので、 (0) = (2π)という条件が要る。 これによって、ν = 0 の時の係数 C は 0 でなければならない事が分かる。 また、ν ≠ 0 の時には √ν が整数であればいい。 その整数を m と置いた方が分かりやすいだろう。
つまり、解は、
となる。 これだけで、ν = 0 (つまり m = 0 )の場合の条件も満たしている。 この2つの項はそれぞれ反対向きに進む波を表しているが、今は極座標なので反対回りの波と表現すべきだろうか。 この2つの波はそれぞれ単独でも解として成り立つ独立なものなので、一つだけ書いて、m の値で区別しておけばいい。
0 ≦ < 2π の範囲で積分したときに1になるように規格化してやれば、結局、この解は
だということだ。
ミクロの世界は不思議なのだから、ひょっとして一周しただけでは波動関数がつながらなくて、二周してようやくつながる場合だってあるかも知れない。 そういう可能性を排除すべきではないが、そんなことはすでに初期の研究者らがあれこれと試してみただろうと思う。 そして、原子を理解する上ではこのような奇妙な考えは必要なかったようだ。 現代人は結果を知っているので楽ができるのだが、感謝を忘れないようにしよう。
身の回りには出来上がった理論ばかりがあるので、理にかなった正しい推論さえ続けていれば全てが説明できてしまうような気分になる。 しかしそれは錯覚だ。 実情は、現実にうまく合うように理論の方を合わせて、「その時点では理にかなってはいたが結局は要らなかった可能性」を次々に捨ててきたという歴史の積み重ねなのである。
ちなみに、何周しても波動関数がつながらない場合というのも考えられる。 しかしこれは定常状態だとは言えないので、今の計算の目的からは外れた別の問題だ。 これについても初期の研究者はあれこれと考えたことだろう。
方向の依存性2
次に2番目の式を解こう。 先ほど √ν が整数 m でなくてはならないとした条件を取り入れると、
という式を解かなくてはいけない事になる。 これは簡単には行かない。 調和振動子の時にやったように色々と工夫が必要だ。 今回はそういう計算テクニック的なところには興味がないので解だけを書くことにする。
式の複雑さには目を向けない方がいい。 規格化の定数が複雑なだけで、本体は最後の関数 Plm(x) の部分だけである。 これは「ルジャンドル陪関数」と言って、その定義は、
である。 この定義の中にさらに Pl(x) という関数が入っているのが見えるだろう。 これは「ルジャンドル多項式」といって、定義は次の通りである。
l や m の値の組み合わせによって項の数や形が全く違うことが分かる。
このような解が存在するのは、l が整数で、λ = l ( l + 1 ) であるときだけである。 さらに l ≧ |m| という条件も満たしていないといけない。
理論的には難しそうだが、具体的に書くとそうでもない。
と の積 を「球面調和関数」と呼ぶ。 これはあれこれ応用問題に取り組んでいると電磁気学にだって出てくるもので、決して量子力学に特有なものではない。
動径方向の解
最後に r についての式を解いてみよう。 前に解いた二つの方程式が、 λ = l ( l + 1 ) であるときにしか解を持たないというのであるから、それ以外の場合について考えることは無意味だ。 そこで、次のような式を解くことになる。
これを解くのも簡単にはいかないので結果だけを示す事にする。
式をなるべく簡単にするために、仕方なく「ボーア半径」
を使った。 これは量子力学が発展する前の推論から作られた量であり、今の話の流れの中で説明するとややこしくなるから、後で補習コーナーで説明しよう。 また、Lts (x) という関数が使われているが、これは「ラゲールの陪多項式」と呼ばれるもので、定義は
である。
本当は解はこれだけではないのだが、r が無限遠になるところで発散するような物理的に意味がないものは捨ててしまった。 そのような条件を課した結果、n が1以上の整数であるときにしか解を持たないようになっている。 しかも、n ≧ l + 1 という条件も成り立っていないといけない。
つまり、電子の軌道はこれまでに出てきた ( n, l, m ) の3つの整数の組で指定されるようなものしか存在できないのである。 n を「主量子数」、 l を「方位量子数」、 m を「磁気量子数」と呼ぶ。
3つの量子数の条件が複雑そうに思えるが、それほど難しくもない。 例えば n = 2 だとしよう。 l は n より小さくなくてはいけなくて、l = 0 と l = 1 の二通りが許される。 m の絶対値は l 以下でなくてはいけないから、 l = 0 なら m = 0 のみ、l = 1 なら m = -1, 0, 1 の三通りが許される。 と、こんな具合だ。 この状況を表にまとめてみよう。
n = 1 ( K殻 ) l = 0 ( s ) m = 0 n = 2 ( L殻 ) l = 0 ( s ) m = 0 l = 1 ( p ) m = -1 m = 0 m = 1 n = 3 ( M殻 ) l = 0 ( s ) m = 0 l = 1 ( p ) m = -1 m = 0 m ...