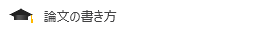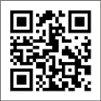資料紹介
運動量表示
波動関数を別角度から見る。
運動量を示すベクトル
シュレーディンガー方程式を立てた時のことを思い出してもらいたい。 波動関数を位置座標で微分して -i を掛けることで運動量を取り出せるのであった。 どうやら波動関数には位置についての情報の他に、運動量についての情報も「同時に」含まれているようである。 前回は波動関数が無限の座標ベクトルの組み合わせで表現できることを確認したが、このように表された状態ベクトルの一体どこに運動量の情報が隠されているというのだろう?
無限の座標ベクトルと直交する別の無限個のベクトルがあって、それらの方向が運動量を表しているなどと考えるのは無理がある。 波動関数は座標ベクトルの組み合わせだけですでに完全に表されているではないか。 もしそんなベクトルがあれば、それは座標ベクトルと区別がつかないものになるだろう。 座標ベクトルだって他の全ての座標ベクトルと直交しつつ無限に存在するのだから。
では座標ベクトルとは直交しない形で存在する何らかのベクトルが運動量の情報を指し示していると考えればいいのだろうか。 とりあえずそれを「運動量ベクトル」と呼び、 |p> と表すことにしよう。 粒子がある特定の運動量を確実に持つという状態にあれば、ある一つの運動量ベクトルの方向を向いていることになる。 当然のことだが、確実にある運動量を持つという状態は、別の運動量を持たない状態であるから、やはりこれらのベクトル |p> どうしもこの空間内で直交して存在していると考えられる。
以上の説明で、位置と運動量を同時に決められないという量子力学の論理構造をイメージとして掴んでもらえたのではないかと思う。 状態ベクトルが、ある一つの座標ベクトルの方向を向きながら同時にある一つの運動量ベクトルの方向を向くことは不可能なのだ。
ではそのような運動量ベクトルと座標ベクトルの位置関係は一体どのようなものなのだろうか。 内積を取れば、0以上1以下の範囲にあることは確かだ。 0と1は含まないであろう。 0なら直交してしまうし、1なら重なってしまうからだ。 しかし現段階ではこれ以上のことは分からない。 別の視点から考え直そう。
指数関数への分解
波動関数から運動量を取り出すときに、微分しても関数の形が変わらないことが大切であった。 関数の形が変わってしまえば、変形後の関数の一体どの部分が中から飛び出してきた運動量の値を表しているかの判別が付かなくなってしまう。 そういうことがないように指数関数を使ったのだった。 指数関数ならば確実にどんな運動量を持つかが調べられる! というわけで波動関数を多数の指数関数に分解して考えてみたらどうだろうか。 何とうまい具合だろう。 実際これが出来るのだ。 次のような指数関数の組み合わせは -π ≦ x ≦ π の範囲内で完全直交系になっているのである。
ただし、このままでは規格化されていないので自分自身との内積を取った時にちゃんと1になるように係数を付けてやる必要がある。 例えば、eix の場合には、
という具合になるが、この計算を見ればどの関数にも同じ係数を付けてやればいいことが分かるだろう。
範囲がこれでは使いにくいというのであれば x のスケールをいじることで、 -L ≦ x ≦ L の範囲で完全直交系になるようにも出来る。 係数も付け直さなければならないが大した作業ではない。
一番左の は運動量が p = π/L である状態を表す。 次は p = - π/L である状態。 順に
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
運動量表示
波動関数を別角度から見る。
運動量を示すベクトル
シュレーディンガー方程式を立てた時のことを思い出してもらいたい。 波動関数を位置座標で微分して -i を掛けることで運動量を取り出せるのであった。 どうやら波動関数には位置についての情報の他に、運動量についての情報も「同時に」含まれているようである。 前回は波動関数が無限の座標ベクトルの組み合わせで表現できることを確認したが、このように表された状態ベクトルの一体どこに運動量の情報が隠されているというのだろう?
無限の座標ベクトルと直交する別の無限個のベクトルがあって、それらの方向が運動量を表しているなどと考えるのは無理がある。 波動関数は座標ベクトルの組み合わせだけですでに完全に表されているではないか。 もしそんなベクトルがあれば、それは座標ベクトルと区別がつかないものになるだろう。 座標ベクトルだって他の全ての座標ベクトルと直交しつつ無限に存在するのだから。
では座標ベクトルとは直交しない形で存在する何らかのベクトルが運動量の情報を指し示していると考えればいいのだろうか。 とりあえずそれを「運動量ベクトル」と呼び、 |p> と表すことにしよう。 粒子がある特定の運動量を確実に持つという状態にあれば、ある一つの運動量ベクトルの方向を向いていることになる。 当然のことだが、確実にある運動量を持つという状態は、別の運動量を持たない状態であるから、やはりこれらのベクトル |p> どうしもこの空間内で直交して存在していると考えられる。
以上の説明で、位置と運動量を同時に決められないという量子力学の論理構造をイメージとして掴んでもらえたのではないかと思う。 状態ベクトルが、ある一つの座標ベクトルの方向を向きながら同時にある一つの運動量ベクトルの方向を向くことは不可能なのだ。
ではそのような運動量ベクトルと座標ベクトルの位置関係は一体どのようなものなのだろうか。 内積を取れば、0以上1以下の範囲にあることは確かだ。 0と1は含まないであろう。 0なら直交してしまうし、1なら重なってしまうからだ。 しかし現段階ではこれ以上のことは分からない。 別の視点から考え直そう。
指数関数への分解
波動関数から運動量を取り出すときに、微分しても関数の形が変わらないことが大切であった。 関数の形が変わってしまえば、変形後の関数の一体どの部分が中から飛び出してきた運動量の値を表しているかの判別が付かなくなってしまう。 そういうことがないように指数関数を使ったのだった。 指数関数ならば確実にどんな運動量を持つかが調べられる! というわけで波動関数を多数の指数関数に分解して考えてみたらどうだろうか。 何とうまい具合だろう。 実際これが出来るのだ。 次のような指数関数の組み合わせは -π ≦ x ≦ π の範囲内で完全直交系になっているのである。
ただし、このままでは規格化されていないので自分自身との内積を取った時にちゃんと1になるように係数を付けてやる必要がある。 例えば、eix の場合には、
という具合になるが、この計算を見ればどの関数にも同じ係数を付けてやればいいことが分かるだろう。
範囲がこれでは使いにくいというのであれば x のスケールをいじることで、 -L ≦ x ≦ L の範囲で完全直交系になるようにも出来る。 係数も付け直さなければならないが大した作業ではない。
一番左の は運動量が p = π/L である状態を表す。 次は p = - π/L である状態。 順に、p = 2 π/L, -2 π/L, 3 π/L, -3 π/L, 4 π/L, ・・・n π/L・・・と続く。 波動関数 がこれらの指数関数をどのような割合で含むのかを計算したければ関数の内積を取ってやればいい。
これはベクトル表現で表せば、
ということであり、こうして求められる係数と、指数関数をベクトル表現したものの組み合わせで状態ベクトルを表すことが出来るのである。 どうやら指数関数をベクトルで表したものが |p> の正体であると考えて良さそうだ。
実際に個々の指数関数どうしは直交してるわけだし、このベクトルは運動量 p を持つ状態を表している。 まさに冒頭で考えたイメージとぴったりではないか。
範囲を制限した波動関数はこのような飛び飛びの運動量を持つ状態の和として表せることが分かった。 逆に言えば、限られた範囲に粒子を閉じ込めてしまうと、その運動量はこのような飛び飛びの値しか取れなくなるということを意味している。
しかしこの粒子は本当の意味で閉じ込められているわけではない。 周期的に同じ形の波動関数が無限に繰り返すことが許されているからだ。 つまり、ここで論じた内容は「周期的境界条件」を適用した場合の状況を表している。 本当の意味で閉じ込められた粒子にはもう少し厳しい条件が付く。
完全に閉じ込められた粒子
完全に閉じ込められた状態というのは、この領域の外側での粒子の存在確率が0であるということであり、波動関数が外側の領域と連続的に繋がるためには x = - L と x = L での波動関数の値が0にならなければならない。
なぜ波動関数が連続していなければならないかを聞かれると少し困る。 シュレーディンガー方程式は微分方程式なので不連続な点があると使えないからだ、と説明すれば何割かの人はごまかせるだろう。 しかしシュレーディンガー方程式は2階微分を含むので、微分したものも連続でなければならないはずではないか、と反論されれば何も言えない。 確かに周期的境界条件を使う時にはちゃんと2階微分の連続にまで気を配っているのだが、「無限の井戸型ポテンシャル」の場合にはそこまではこだわらない。 まぁ、ある地点を境にいきなりポテンシャルが無限大になるという仮定自体が不自然なものなのでそこは飽くまでも近似ということで大目に見てもらいたいところだ。
自然界には一見不連続に見える現象は数多いけれども、数学的に厳密に不連続になるようなことはなく、その不連続に見えるぎりぎりの領域を拡大して調べてやると、実に色んな振る舞いが見られるものである。 例えば水と空気の境目は不連続のようだが、そこはくっきり分かれているわけではなく、水分子と空気分子の激しい運動、蒸発と凝固、さらに細かく見ればそこには複雑な電子の営みがあって嵐の時の海のようになっているわけだ。 電子回路のオンとオフには明確な違いがあるが、その瞬間に起こる過渡現象は実に微妙で連続したものである。 ある一定の温度、ある一定の濃度で性質が激変する化学物質の構造も、何の前触れもなしに変化が完了するわけではない。 もしそういう中間状態のない厳密な不連続があるとすればそれは「特異点」と呼ばれて非常な議論の対象になるだろう。
話を戻そう。 ある領域内にのみ存在する粒子の波動関数の値が両端で0にならなければならないとすると、許される波の種類はそう多くない。 sin 関数か cos 関数、あるいはそれらに虚数 i を掛けたものが候補となる。 ちょっと工夫してやれば指数関数の簡単な組み合わせで cos 関数を表現することができるのだが、例えば次のような具合だ。
先に話した条件に合うためには本当は cos x ではなく、奇数 n を使って cos n ( π / 2L ) x とせねばならないのだが、そうするとやたら複雑な式変形をしている印象を与えてしまうので、式変形の本質が分かるように略して書いてみた。 これは運動量が p = n ( π / 2L ) を取る状態と p = - n ( π / 2L ) を取る状態の重ね合わせを意味している。 つまり粒子が閉じ込められた状態では、運動量が p を取る状態と -p を取る状態が同じだけの割合で重なっていなければならないのである。 この結果は面白いほど理にかなっている。 右へ行く粒子が観測される割合と左へ進む粒子が観測される割合がいつも釣り合っており、確率の言葉を借りるならば「この状況での運動量の期待値は0」だということだ。 長期的に見てどこかへ行ってしまうことはないというイメージであり、まさに束縛された状態を表している。
同様な方法で sin 関数も作ることができるだろう。
これも n が偶数という違いだけで、許される運動量はさっきと同じ式で表されることになる。 2つの指数関数の係数の符号が違うので、右向きと左向きが同じ割合で重なってはいないのではないかと不審に思うかも知れないが、実際に観測される確率は係数の絶対値の2乗で決まるのだからそんな心配は無用である。
連続的な運動量
もし波動関数が周期的ではなく、有限の範囲を越えて無限の彼方まで存在するものだったらどうだろう? 無限の範囲に横たわる関数を別の周期的な関数で展開してやるためには連続的な和、すなわち積分が必要なのであった。 つまりあらゆる連続的な波長を持つ基本波の重ね合わせによってしか表現できなくなってしまう。 すなわち運動量も座標のように連続値を取るようになるわけだ。 その時の係数も連続的に変化する量を考えなくてはならないので、 のような関数を使うことになる。
ここに出てくる関数 の絶対値の2乗は、粒子の運動量を観測した時にその値が p として見出される確率を表すものであり、波動関数に良く似たものである。 それでこの運動量の分布を表す関数 を「運動量表示の波動関数」と呼ぶ。 普通の波動関数 は「座標表示の波動関数」だとい...