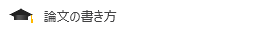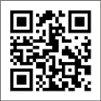タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
C・ラッセル(編)渡辺正雄(監訳)成定薫・大谷隆 共訳『OU科学史。 宇宙の秩序』
創元社、1983年、355頁。
(紹介)
イギリスの公開大学(Open University)の科学史テキストScience and Belief: from Cpernicus to Darwinの邦訳『OU科学史。 宇宙の秩序』の刊行にあたって、第。章「科学史へのさまざまなアプローチ」、第」章「ガリレオとカトリック教会」の訳出を担当した。
筆者は広島大学総合科学部で「科学史」の講義を担当しているが、学期の初めに次のように言うことにしている--「この講義を通じて私が目指しているのは、皆さんが、自覚してであれ無自覚であれ、抱いているであろう科学/科学者像に揺さぶりをかけることです」。受講生は教壇からの「挑発」の真意を図りかねて困惑している。実際、半期十数回の講義を通じて筆者は意図的に極端な内容を展開するのだが、期末試験の答案内容から見る限り、大半の受講生にあっては、「科学史」受講以前と以後とで科学/科学者像の転換は起こらないようである。かくて、筆者は自分の講義の教育効果のなさを遺憾に思うと同時に、受講生がいかに堅固な科学/科学者像をもっているかを繰り返し思い知らされることになる。
さて、科学史を受講しにきた学生諸君の多くが抱いているであろうと筆者が想定し、実際、筆者のささやかな努力にもかかわらず彼らが堅持し続ける科学/科学者像とはどのようなものであろうか。それは、科学知識は客観的かつ普遍的であり、科学者は無私の立場で黙々と研究に勤しんでいるとする、古典的な、敢えて言うなら美化され聖化された科学/科学者像である。T・クーンの『科学革命構造』(みすず書房)以前の科学/科学者像とも言えよう。この旧態依然たる科学/科学者像は、現在も初・中等教育はもちろん大学教育を通じても拡大再生産されており、マスコミ、ジャーナリズムもその普及、強化に未だに尽力している。例えば、ガリレオは地動説を奉じたため、異端審問に付され、厳しい取り調べに屈して節を曲げたとはいえ、「それでも地球は回っている」と叫んだ科学の殉教者であり、一方、ガリレオの弾圧に狂奔したカトリック教会、そして一般に宗教は常に科学の進歩に敵対してきた、といった善玉・悪玉史観は現在も根強い。
このような状況の中で、科学理論の転換は、旧いパラダイムを支持する科学者集団と新しいパラダイムを支持する科学者集団のせめぎ合いから生じ、このせめぎ合いの中で宗教が思想として、また組織としてどのような役割を果たしたかは個別に検討せねばならない、などと論じても受講生にはピンとこないのも仕方あるまい。また科学者の人間的側面、例えばガリレオが木星の衛星を「メディチ家の星」と命名して、当時、ヨーロッパ君臨していたメディチ家の寵を得ようとしたエピソード、あるいはニュートンがフックやライプニッツと先取権争いをしたエピソードなどを紹介すると、「夢が壊れてしまった。こんな話は聞きたくなかった」などという感想を洩らす学生が出てくるのもけだし当然というべきであろう--夢を壊してしまったのは申し訳ないが、彼ないし彼女には筆者の講義の狙いが多少なりとも通じたことになる。
しかし、本書の刊行によって、ゴマメの歯ぎしりとも言うべき筆者の努力は少しは報いられるかもしれないと期待している。というのも、本書の主題は「科学と信仰」であり、科学革命期に活躍した科学者たち--ガリレオ、デカルト、ニュートン--の科学上の業績と彼らの信仰ないしは宗教的立場の関連が近年の科学史研究の成果を踏まえて、かなり詳しく、しかも説得力をもって論じられているからである。その結果、科学と宗教に関する前述したような「ホイッグ主義的理解」が完膚無きまでに論駁されている。したがって、もし受講生が丹念に本書を読むならば、それだけでも通俗的な科学/科学者像は大きく揺さぶられるはずである。筆者は本書の記述を前提にして、例えばコペルニクスについて、彼の人間性や科学上の業績を批判的に論じているA・ケストラーの名著『夢遊病者たちの』の部分訳『コペルニクス』(すぐ書房)を紹介したり、ガリレオの望遠鏡と天文観測の「科学的根拠」をめぐるP・ファイヤアーベントの論議(『方法への挑戦』新曜社)に言及することができるわけである。受講生の反応が楽しみである。
資料提供先→ http://home.hiroshima-u.ac.jp/nkaoru/OU.html