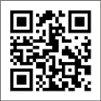漱石『こころ』にあらわれる女性像と恋愛像
漱石『こころ』にあらわれる女性像と恋愛像


- 550 販売中
内容説明
漱石の女性像と恋愛像について、その転換期と考えられる『こころ』を中心に置いて考えていきたい。
『それから』から『こころ』までの作品における女性は、「寡黙な女性」であった。言葉を奪われ、自らは語らず、男によって勝手に解釈される存在であったのだ。そこには、「まなざす男」と「まなざされる女」という構図があり、女性は、「謎めく」「不気味」「純白」といった多義性を備えた存在であった(この「純白」という部分については、武田充啓「無垢なるものの行方(一)―夏目漱石『こゝろ』を中心に―」(2003)を後ほど参照する)。この特徴は『こころ』においても極めて顕著であり、川島秀一(2000)も「漱石の女性表現―文化テクストとしての〈漱石〉―」の中で、『こころ』について以下のように論じている。
そしてここで、他のどの作品にもまして特徴的なのは、その「お嬢さん」という女は、その恋愛の渦中にありながら、その言葉はまったくと言っていいほどに締め出されています。逆に言いますと、そこに繰り広げられる男の世界とその物語は、そのようにして〈女〉の言葉を締め出し閉ざすことを前提に成り立っています。
確かに、この『こころ』(特に「下 先生と遺書」について)は、二人の男の女性をめぐる話であるにもかかわらず、当の女性の言葉、つまり当人の意思というものが全然前面に出てこない。ただし、このことは女性が男性に対して力を持たないということを意味しているわけではなく、男同士のコミュニケーションから排除された「お嬢さん」が、同時にそのコミュニケーションを脅かす存在でもある。