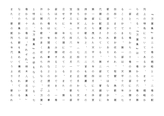全ての資料 / タグ / 仏教
資料:191件
-
 漢文学 第2設題
漢文学 第2設題
- A評価
 1,100 販売中 2009/11/24
1,100 販売中 2009/11/24- 閲覧(1,817)
-
 武士道に置いての「義」の意味
武士道に置いての「義」の意味
- <序章> 私は卒論のテーマを何にするかと具体的に決めているわけではない。しかし、今回は「武士道」という姿勢に注目してみることにした。 それは、武士道が単に、日本の歴史上に存在した武士達の生き様を映しているのではなく、日本には数知れない宗教は混合している中、神道、...
 550 販売中 2006/11/07
550 販売中 2006/11/07- 閲覧(4,218) コメント(17)
-
 インド仏教の衰亡について
インド仏教の衰亡について
- (1)インド仏教衰亡説 インド仏教の衰亡を説明するものとして、イスラム教徒主犯説、自然衰退説、人類学的視点からの研究などがある。しかし、その本格的な検討は未だ行われていない。 さて、インド仏教の衰亡という認識は、社会的な存在としての消滅という視点に立っている...
 550 販売中 2006/05/30
550 販売中 2006/05/30- 閲覧(2,202)
-
 儒教的死生観 中国哲学レポート 評価A
儒教的死生観 中国哲学レポート 評価A
- 中国哲学の授業で提出し、A評価を頂いたレポートです。 「儒教的死生観とは何か」と言うテーマで、日本人の死生観と照らし合わせながら論じました。 参考文献を参照しながら、2400字程度で論じています。 学習に役立てていただければ幸いです!
 550 販売中 2018/07/31
550 販売中 2018/07/31- 閲覧(5,105)
-
 【2016年度合格リポート】Q0705 国際政治学 第2設題 B判定
【2016年度合格リポート】Q0705 国際政治学 第2設題 B判定
- 佛教大学の通信教育課程で、2016年度にB判定にて合格したリポートです。 コードは、高等学校地理歴史、公民、中学校社会課程のQ0705です。 コードが違っても、設題が同じ場合はご参考にして頂けるかと存じます。 第2設題についてまとめております。 テーマは貿易を選択しております...
 550 販売中 2016/12/15
550 販売中 2016/12/15- 閲覧(2,395)
-
 佛教大学 日本文学史 設題1(C判定)
佛教大学 日本文学史 設題1(C判定)
- 上代、中古、中世、近世の文学の特質を、それぞれの時代の特性をふまえつつ、下記の諸作品を例にして具体的に説明せよ。〈古事記・万葉集・古今集・女流日記(女性によって書かれた日記)・源氏物語・平家物語・徒然草・近世小説〉
 550 販売中 2010/11/29
550 販売中 2010/11/29- 閲覧(1,528)
-
 日本文学文化概説A1課題2
日本文学文化概説A1課題2
- 『万葉集』全二十巻の概略と一、二巻の配列上の特色についてであるが、まず、概略から述べる。『万葉集』は、一巻から十六巻の第一部と、十七巻から二十巻の第二部に分類することができる。第一部は、天平十六年(七四四)までの歌が収められ、相聞、挽歌、雑歌の部立がされており...
 550 販売中 2010/03/16
550 販売中 2010/03/16- 閲覧(1,754)